若手演出家コンクール2022 優秀賞受賞者インタビュー〈広報部〉 西田悠哉
西田悠哉(劇団不労社)『生電波』
―― いよいよ幕が開きました
西田
小屋入りしてから本番までの時間が史上最短で、自分でも音響の仕込みやオペレーションをやりながら演出としても動かなければいけなかったので、息をつく間もないまま今、という感じですね。

―― 今回のタイトル『生電波』の「生」の意味を教えていただけますか?
西田
この作品は劇団としても初めての試みとして、劇団員の永淵さんとの共同脚本で臨んだ作品です。一緒に書き進めていく上で、まずはタイトルから決めようとアイデア出しをする中で、「電波」という単語が出てきました。僕たちがホラー好きということもあり、電波を幽霊のような「日常にあるけれど知覚出来ない存在」として表現したらどのような世界が見えるか?という点を、作品の中心となるビジョンとして据えました。そこで、肉体を持った生き物として、更には演劇のライブとしての「生」という接頭辞をつけて、このタイトルになりました。
―― 電波を演劇作品にしようとしたきっかけはなんでしょうか?
西田
変な話ですが、昔よりも年々頭が鈍ってるような感じがしていて、その原因を探っている中で、いわゆる「スマホ脳」の話なども見聞きするようなり、それから電波と自分の関係について考えるようになりました。
例えば、僕たちの団体は1993年前後に生まれたメンバーで構成されているのですが、この世代は最後のテレビっ子世代だったと思います。スマートフォンが普及したのも高校生の終わりくらいで、それまで小学校や中学校の頃なんかはテレビを中心に話題が回っていたし、自分の語彙や会話の作法までテレビから受けた影響はかなり大きいと思っています。
それから、コロナ禍になって頻繁にラジオを聞くようになりました。本当に人と喋る機会がなくなった時に、ラジオがその隙間を埋めてくれたんです。話している距離は物理的には遠いはずなのに、イヤホンを通じてすぐ近くどころか頭の中で喋っているように、会話が立体的に立ち上がるような感覚があって、このバーチャルな体験に魅力を感じています。
スマホやPCも含め、自分の人生や生活のそう少なくない時間に現在進行形で関わっている電波という存在。この中毒性や刺激の強さ、無意識下で頭を侵食される感覚を演劇にしたらどうなるのかというイメージが『生電波』の着想としてありました。

―― 作品の中に、怒りのような物があるように感じたのですが
西田
そもそも作品を通じて電波を批判したりとか肯定したりという意図はないのですが、厳密に言うと、怒りというより悲しみのようなものはあったかもしれないです。
一般的なドラマの様式として、自我や主体を前提とした登場人物たちが、ある問題や課題に対峙し、それを乗り越えるべくアクションを起こすというモデルがあるかと思います。
けど、先ほどの無意識下の電波の影響の話から考えても、果たして人間はある問題に対して主体性を持って適切に行動できるのか、さらに言うならば、人間の行動は自分自身では選び取れず、世界の事象に複雑な形で影響を受けているではないのか、という問いがありました。 このような議論を永淵さんとしている中、共同で書き進めていく上で、人間中心の考えから逸脱した「アンチ・ヒューマニズム」の方針を打ち出しました。
例えば今回の話でも所謂「陰謀論」なるものに、人生が左右される人が出てきます。
陰謀論にハマってしまう人って、社会的には変な人や可哀想な人だと思われがちですが、そもそも自分たちが認識する世界だって、それこそ電波などを通じて見聞きした情報から暫定的に組み立てているだけで、どこにも根拠や正当性はないはずです。 その地盤の危うさが種々のトラブルを生んでいると思いますが、これは個人の意志や力で乗り越えられない部分も大いにあり、その無力感に対しての悲しみや絶望はあったかと思います。
自分が劇を作る上で大事にしているポイントとして、どこからが異常でどこからが正常かというラインをこちらで引かないようにしているのですが、今回もお客さんに対して自分の立ち位置や線引きの境界を揺らがせ続けるような構成を意識しています。
まぁでも怒りもありますね。スマホがなければもっと色んな能力が開花していたのかもしれないとか(笑)
コロナ禍で一人になった時に考えたんです。自然が作り出す肉体のあるべき姿とか、生物としての強度が本来あったはずなのに、電波に狂わされてしまって、その歯止めもきかない。 Twitterを気にせずにいたいけど気になってしまうとかも含めて、頭と体が一致しないストレスは作品の原動力にあったかもしれません。
―― 電波の中にSNSが入っていましたよね?
西田
現代社会で電波をモチーフとして描く上で、SNSの存在は避けて通れないと思います。劇中では広告のアルゴリズムの話も出てきましたけど、結局現代人の行動選択が、第三者から与えられる情報で容易く転がされてしまうという面は「アンチ・ヒューマニズム」の発想の起点の一つでもあります。
―― 美術について教えていただけますか?
西田
今回の美術の2つの大きな要素として、段ボールとアルミホイルを採用しました。
例えば今回のコンクールのように、どこでも上演できる劇を作りたいという狙いが作品づくりの当初からあったので、持ち運びのしやすさや調達のしやすさは、これらを選んだ理由として大きいです。 物を置くだけで舞台が完成して、且つ複数の意味合いを持つような素材であることも大事です。
この作品では、登場人物である兄弟の引越しの荷物と一緒に、電波に関わる機器を段ボールで表現しています。
段ボールは中身を入れなければ、基本的にそれ自体では機能しませんが、例えば引越し時に荷物を梱包することで真価を発揮します。
そこに何かを入れた時に機能するという意味で、電波がなければただの「箱」となってしまう電化製品を段ボールで表現することで、その性質が浮き出るかと思いました。
付け加えると、人間も電波を介して情報を出し入れするという意味である意味「箱」のような存在だと言えます。さらに演劇における俳優という役割も、台詞を入れて発信することで何者にでもなれるという意味で、電波の送受信機のように思えます。 そういった「箱」性を演劇的に際立たせる上で、段ボールが適していると考えました。
アルミホイルについては、演出上のポイントでもあるんですが、リアルワールドと電波世界の二つがパラレルに展開する作品にしたかったので、電波の存在をどうやって表現するか試行錯誤する中で生まれたアイデアです。
アルミホイルも段ボール同様、日常的に使われる素材でありながら、電波を遮断する物質として、メタ的な意味の広がりを併せ持っています。 さらに煌びやかな絵力やヒラヒラした浮遊感も含めて、劇世界に独立した電波存在を表現する手法として面白いと思いました。
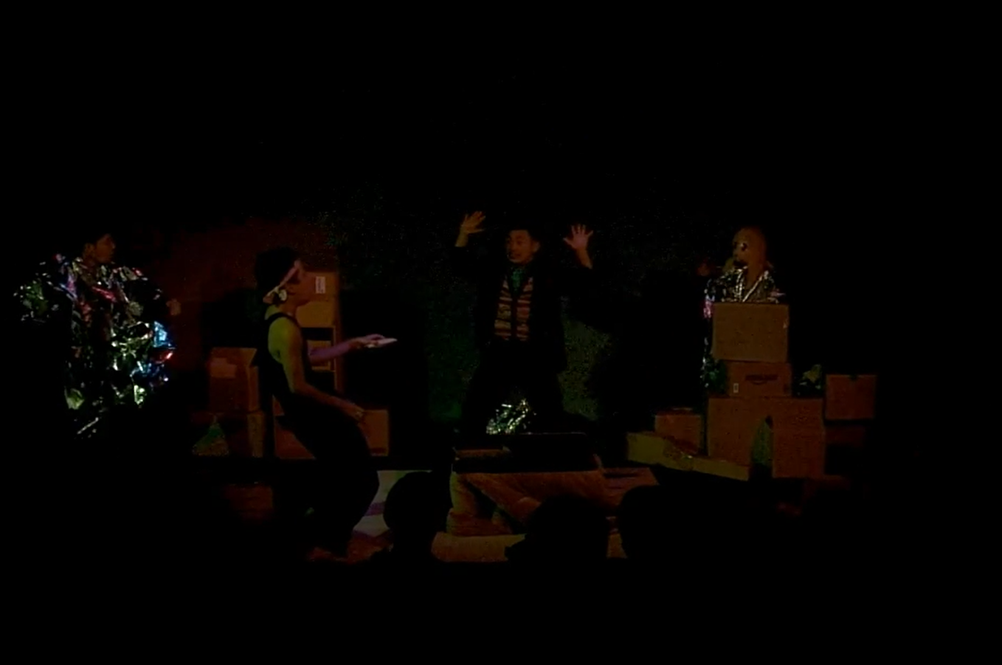
―― 劇団の名前の由来と今後の展望を教えていただけますか?
西田
由来は、僕が大学生の時につけた名前なので、単純に働かずにフラフラしていたいという一心でつけただけです(笑)
劇団員はみんな働いているので今や有名無実になっていますが、僕は今、仕事を辞めて大学院生になっているので、僕だけリアル不労者ですね……(笑)
後付けとして、「フロウ」っていう言葉が持つ意味合いについて考えてみると、英語の「FLOW」といいう言葉は「流れる」という意味があり、奇しくも日本語の「浮浪」や「不労」とも音の上で意味が重なってきます。
この定まらないイメージ、漂流するような感覚は大事にしていきたいと思ってます。
僕達は関西を活動拠点としながら、大阪の劇団なのか京都の劇団なのかも微妙なまま、京阪神をフラフラしているのですが、今後どんどん関西の外にも「フロウ」して、もっと色んな人と出会って、最終的には海外にまで流れ着きたいと思ってます。
聞き手 日本演出者協会 広報部 桒原秀一
