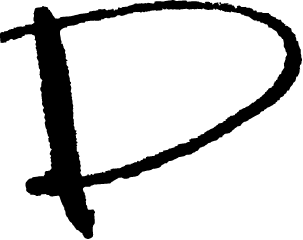特別対談:
藤田俊太郎×五戸真理枝
《第2部》
インタビュー

シェイクスピアに女性の武人……
戯曲を疑うことで見えてくる新たな価値観
藤田 そうですね……。近未来というのは非常に近くて……、というのはですね、3世紀から5世紀のブリテンを軸としたお話なんですけれども、カンパニーの皆さんとスタートとして共有したことは、シェイクスピアが敢えて時代を設定した意味を考えたいという事でした。
当時のローマ中心の世界地図を考えると、ブリテンってものすごい田舎なんです。要するに世界の隅っこというか、イギリスは別にそこまで大国じゃない、って考えたときに理解できた事がたくさんありました。馴染みのある共通の光景がない、国と時代。そう考えるとこれは3世紀から5世紀を書いた近未来もしくはあり得たかもしれない世界の話と捉える事もできる。あり得たかもしれないリア王の物語だと考えた時に、女性が普通に武人をやっているという世界に辿り着きました。そもそもリア王って長女ゴネリルと次女リーガンの財産分与が先頭に立ってるわけですよね。そう考えると女性が元々この国を動かしていることは明らかであって、結果そこに何か読み解きのヒントがあるんじゃないかなと思い、翻訳の河合祥一郎さんにも相談しました。道化とコーデリアを1人の役者が演じる事はシェイクスピア時代では一般的でした。また全役、男性の役者だけで演じているわけですから男性の価値観で物が作られていきがちだと思うし、マクベスやハムレットやオセローやリア王はみんな男性ですよね。ここにあり得たのかもしれない女性史とかが新しい価値感を生み出す可能性をこの作品も内包しているんではないか、というところに着眼点を置いて、武人の女性がエドガーを演じるという仕掛けで構築されていった、というのが稽古に入るまでの演出プランです。
で、稽古では今話したような話題を何度も話してるんです。このあり得たかもしれない未来像を稽古を通して言語化していく。そういう事が出来たのは、カンパニーの皆が共通してシェイクスピアの世界を固定概念に捉われないイメージとして持てたという事かもしれないです。すごく価値観の違う方々が集い、それぞれに確固たる考えがあるからこそ、違いを受け入れながら対話できた事も良かったと思います。

五戸 それはすごい大変そうですね……。
藤田 それが狙いだったというか、いわゆるリア王演じる木場さんが役者として辿ってきた歴史と、女性コロスの皆さんの演技者としての経験、辿ってきた歴史とかって全然違うわけですよ。各々の価値観が遠いカンパニーほど、その中の共通言語をどう見つけていくかが面白いとも思っているので、一つ一つの対話を丁寧に重ねていきました。
木場さんとは稽古始まる数ヶ月前からかなり話していました。木場さんにはやりたいリア王のイメージがあり、提示するので見てほしいと最初にお話がありました。木場さんとは演出助手の時代からお付き合いがあるんですけれども、御自分で61年間思い焦がれたリア王の姿がありました。小学校から中学校になる時にリアを演じる機会があったと、その後に今の松本白鸚さんのリア役の時に道化を演じている。様々な道筋を辿ってこられて、自分がシェイクスピアのリア王をやるならば、既存の考えには囚われないという強い想いが最初からあったんですよね。
五戸 かっこいい。
藤田 世界中で演じられてきたリア王と同じ道を辿らないことを、かなり明確に言語化してくださった上で稽古に臨んだので、すごく良い仕事ができたと思います。結果として、今回稽古場から舞台稽古まで、木場さんへのプロンプはほとんどなかった。もう完璧に台詞が入ってから稽古に来ていたので……。
五戸 すごい……すごすぎる……。
藤田 皆さん焦りますよ。なんだ…!? と(笑)。
それから、それぞれの人物のあり方というのは大きく話しました。後は、稽古を進めていってこのシーンは時間が必要だなという所は、そのシーンにいる方に来て頂いてじっくり対話しながら作っていきました。それを通し稽古でまとめて、上演時間を少しずつ短縮していくっていうプロセスでした。だから、対話は実によくしましたね。シェイクスピア、言葉の演劇ですから、もちろん稽古場でも対話が必要なんですけど、その対話というのは、セリフに何が書かれているかよりも、そこに至るまでの感情の過程とか、相手の言葉を受けた上でどのように変化していくのかという事を話しましたね。皆とお互いの意思疎通ができたなという風に思います。そこに翻訳の河合祥一郎さんが細かくカットとか直しの為に稽古場に伴走してくださって、今回は新訳の初演ですから、そこのスタッフワークも実に合致していたと思います。初めてお仕事をするスタッフの方が多かったんですけれども、KAAT 神奈川芸術劇場の皆さんが特設会場を作ったり、客席をデザインして構築してくださったので、その部分での対話も良くできたと思える進め方でした。
五戸 はい、もうなるほどというか、目に見えるような感じです……。
藤田 稽古を重ね、戯曲の内容に関して分からない事や自分で解釈しきれてない事は、素直に分かりませんと言いました。その方が同じ目線で藤田はやろうとしているんだなっていう風に皆さんが思ってくださるので。あとは特にコロスの皆さんとどれだけ話すかってことも大事でした。コロスを観客代表というつくりにしたので、話しながら僕自身たくさんの発見をしていきました。
あえてト書きを読む……
ト書きが音楽のように聞こえ、会話が際立つ
藤田 五戸さんは『石を洗う』の稽古をどうやって進めたんですか?
五戸 そうですね。これは書き下ろしなので、私が宮崎に行って劇作の永山智行さんがどんな所で書いてらっしゃるかを見てきたり、あとはこれはいつも永山さんがなさっていることらしいんですけれど、永山さんに出演者の皆さんと会ってもらってインタビューしてもらったりとか。
藤田 という事は当て書きですよね。まずどうして永山さんとお仕事されることになったんですか?
五戸 これはですね、実は文学座の文芸編集室の徳田玲子さんという方が永山さんの戯曲集を読んで、徳田さんがこれは文学座でやるべきだと企画を立てました。
藤田 なるほど。
五戸 私、ちょうどその年に自分で企画を出していなくて、演出を依頼された、というのが最初の経緯です。でも戯曲を読んでみたり、宮崎に行ってみると、うお……これはすごい……、というか、今までにない文体ですし、まずト書きをどうするのかを考えるのが楽しそうだなと思って、私も楽しみに意気揚々と企画に参加しました。
藤田 ト書きを読むって、モノローグになりそうですよね。
五戸 はい。出演者の中の年長の3人は80を超えてるんですけども……。
藤田 そうですよね。
五戸 1番上は82歳なんです。
藤田 え!?
五戸 だから、覚えられるんだろうかみたいな、台本の完成を待っている間に戦々恐々としてくる空気感もありますし。
藤田 え? 稽古初日に台本はなかったって事ですか。
五戸 ありましたけれども、最後まできたのが、稽古初日の2週間前くらいだったかな。
藤田 稽古初日の2週間前ですか?
五戸 それくらいですかね。
藤田 しびれます。
五戸 結構……、そうですね。
藤田 皆さん、プレッシャーがあったのでは。
五戸 覚えるにはギリギリだったんです。ト書きを誰が読むか決まってないから、とにかく早く決めてほしいと言われていて。割り振りとか結局やりながら進めたって感じなんですけれど、その中でも、 “この世界は祈りでできてるんだ” というテーマが私にはすごく響いて、だからもうそれをみんなで信じて突っ走るといいますか……。これを演出する前に沖縄に行っていて、いかに地方で起きていることが東京に伝わりにくいかみたいな事も物すごく身をもって感じていたんですね。なので、この戯曲にはそれを伝える使命もある。そして必ず面白い作品になると思うという事を延々と語り尽くし、まずドキドキ感を払拭するエネルギーを共有して、目的の共有をするという所から始まりました。
藤田 どういう系列に入るんですか? ト書きを読むっていうのを僕は初めて聞いたので。日本演劇史のどこに入るんですか?
五戸 私も初めてですけど、落語を見て思いついたらしいです。
藤田 なるほど、落語……、確かに落語が近いですね。
五戸 そうなんです。
藤田 もしくは、講談ですか……。講談にも通じると思います。
五戸 永山さんご自身が主宰されている「こふく劇場」は、みんながすり足で動いたりですとか、すごく様式化された演出をされるんです。例えばト書きも3人ぐらいが全員で一緒に言ったり、それもメトロノーム120とか一定のテンポで稽古するって聞きました。「こふく劇場」の公演は観たことあるんですけど、それはそれでものすごい荘厳で、ト書きが言葉なんだけれど音楽のようで。でも、その中でやっぱり会話が際立つような、とても独特な印象でした。
藤田 勉強不足で申し訳ないのですが、今回の観劇で、永山智行さんを初めて知りました。ジャンルとしてあるのか、興味深いと思っているのですが……。
五戸 鈴木忠志さんとか太田省吾さんの本をよく読んでいらっしゃるとお聞きしました。
藤田 はい。なるほど、です。
五戸 でも作家でもあるので、作家の時は取材対象に対する敬意の払い方が尋常じゃなく、取材した事に嘘を入れられないと仰ってました。なので、台詞がとても生々しいというか……。ドラマにしようとしてないんですよね。私が劇作を勉強した時に学んだ理論が台詞に全く入ってないなと……。
藤田 わかります。
五戸 面白くする為に書いてない。なんていうか、そこにいる人にリスペクトするみたいな書き方だなってすごく感じましたね。それを「こふく劇場」の場合は出演者が若く、80代の登場人物がいても40代の人が演じるのである距離が生まれるんですよ。でも文学座の場合は本当の80代が演じたりするので、距離がない(笑)。
藤田 鵜澤秀行さんと寺田路恵さんのお芝居、涙なしでは観れなかったです。
五戸 本当にすごい共感力でした。寺田路恵さんは台本を記憶するのが誰よりも一番早かったんです。立ち稽古初日には完全に全部覚えていました。若さがなくなってきた分、どうやって補うかみたいな、先輩たちの裏の苦労みたいなのをすごく感じて、毎朝稽古開始時間より早く来て台詞合わせしてるとか、80代の先輩方がやってるんですよね。これが俳優魂か! じゃないんですけど、全然おごるんじゃなくて面白いもの作りたいっていうか、良い芝居がしたいということに対して、どれだけ誠実なのかっていうのを感じました。文学座のやり方で永山さんのあの戯曲を立ち上げるには、その出演者の姿をそのまま見せるしかないので、そこら辺はあまり演出をつけず、会話だけはちゃんと構築するようにやりました。

藤田 なるほど、白いコートを着たりっていうのも演出ですよね。
五戸 あれはそうですね。最初は福島で作業している白い防護服が浮かんだんですよね。それが結局、レインコートになりました。
藤田 レインコート。自分は東北出身なので、やっぱりすごい重要でした。ある種のドキュメンタリーみたいな要素もあるんですよね。
五戸 そうですね。やはり会話の部分が取材を元に作られているっていうのがあるのかもしれないですね。
藤田 そこが良かったですね。
五戸 多分、他の劇作家の方にはこういう書き方は怖くてできないんじゃないかと思うんですよね。
藤田 できないですよね。起承転結とか、いわゆる書き方のセオリーというものから違う文脈で作られているんですよね。
五戸 そうです。
藤田 不思議です。でも稽古は大変だったと思います。当然、出演者の中には先輩とかもいらっしゃいますよね。
五戸 そうです。例えば、鵜澤さんは私が研究所の研究生だったときに主事だった方で、当時私はバイトをしていたんですけど、授業料を滞納していたときに「50円ずつでも良いから払いなさい」と分割をさせてくれた先輩だったんですね。
一同 (笑)
藤田 そういう先輩と、演出家との関係になるとどういう風な事になるんですか?
五戸 普通に演出家として見てくださいます。なので、私の方がとても変な感じっていうか……。
藤田 作品に流れる空気がとてもフラットだなって思ったんですよ。皆さんの演技がすごく素直というか、そのまま生々しく喋ってらっしゃったので、それは演出家と良好な関係がないと、この状態にならないなっていう風に思ったんです。
五戸 皆さん、ちょっとここがやりにくいとか、そういう事もはっきりと仰ってくださるので、わかりやすいです。黙ってかしこまっている人たちじゃないというか、それはとてもやりやすい事だなと思います。
藤田 五戸さんは、稽古場でもこんな感じの柔らかい方なんですか?
五戸 こんな感じですね。
藤田 それはすごく良いですよね。話しやすいですよね、役者からすると。
五戸 本当ですか?
藤田 親しみやすさは大事ですよね。何でも言えるっていう事が大事だと思ってます。
五戸 そうですよね。
藤田 僕は役者が「言いづらい台詞があります」って言いたいけど、言えない、って状況を作りたくないです。
五戸 そうなんですよ。
藤田 色々と話せて、役者のモチベーションが上がれば芝居が変わりますよね。
五戸 そうです。
藤田 素敵です。下手に出るわけじゃなくて、風通しがいいというか、役者側の年齢やキャリアも関係なく、言いやすい空気を作ってらっしゃるのは素晴らしいと思います。
五戸 風通しを良くしようと心がけていらっしゃるのは藤田さんも同じなんだなと、さっきの話を聞いて思いました。やっぱり同じことが多いですね。
藤田 やっぱりこれって演出助手の経験ですよね。できるだけ言いやすい空気を作るのが大事だなっていう風に、かつてずっと感じてました。
劇場とは真実の感情に出会う場所
今後のビジョンをお伺いできますでしょうか?
藤田 自分の仕事は一体何かって考えると、演劇を作る事で……。それで生の重要度とか、喜怒哀楽を他者と共に想像する事ができるのって、やっぱり劇場だと思うんですよね。そこには僕が考える “真実” があるんですよ。リア王にももう一つ大きなテーマがあって、 “真実を語れるもの” と “真実を語れないもの” なんです。リアに真実を伝える人、真実を伝えられなかった人、真実を伝えることを拒絶した人っていろんな真実という言葉を司る者が劇中にいます。劇場はやっぱり “本当の言葉” とか、自分の “真実の感情” に出会える場所だと思うんです。すごく愛しい場所だし、お客様と出会える場所をとても幸せに持続したいって思います。それが今できる全てかなと。もちろん劇場だけがそうではなく、そこに至る過程も大事だと思います。稽古場で俳優と対話し、スタッフと対話し、自分はこういう物を作りたいんですって、お互いのその時の感受性を持って対話し合えば物を作れるっていう、それが劇場だなって思っているんですね。
物語っていう観点でいくと、僕はやっぱりリア王のような壮大な物語を演劇として作っていく事って、当たり前のようでいて、新しい価値観を持ちながら上演するのはとても大変な事だと思いました。もちろん創作する喜びの方が大きく、新しい事に挑戦して、大きな物語が喪失しないようにしていきたいなという風に思います。僕自身、10代の頃から読んでいる本が基本的に変わらないんですね。例えば、夏目漱石の『こころ』は10代、20代、30代、40代で感じる内容がまるで違います。僕は10代の頃にすごく時間あったので、ヴィレッジヴァンガードのバイトだけをやっていたので(笑)。
一同 (笑)
藤田 その頃から『こころ』とか『罪と罰』とか、『銀河鉄道の夜』、あと『百年の孤独』とか。黒澤明監督の映画とか、フェリーニ、キューブリックの作品、『ゴッドファーザー』等を見ていて、その映画の世界が自分の演出の礎にあります。共通してるのは大きな物語であること。愛や家族や人を見つめた大きな物語は僕の中で残り続けています。とはいえ、小さな物語もとても面白いし、現に、ちょっと文脈からそれるかもしれないんですけど、今の自分より下の世代は正直、YouTubeやネット配信の方が身近で、もしかしたら大きな物語に深く接していないかもしれないんですけど、そういう20代の役者やスタッフと話すと、自分とは感性が違って面白いなって思うんですよ。『石を洗う』も20代の感性と演技が面白いじゃないすか。
五戸 面白いですね。
藤田 だから僕は今後の目標としては、大きな物語と小さな物語の間で存在している物づくりの中で、劇場の真実を見つけていきたいと思います。大きな物語だけじゃないし小さな物語の集積だけではなくて、その中に両方の価値観を持ったような演劇やミュージカル。ちょうど、自分の上の世代と下の世代、中間にいるので、相違点を挙げて分断するのではなくて、お互いの価値観を受け入れながら何か新しいものを作れる。僕はそれを融合して作れる立ち位置にいるんじゃないかなと思って、自分に課して背負いたいなっていう風に今は思っています。
五戸 私はやっぱり……、本当は今も劇作家になりたいので、現代の難問について物語にしたいと思っているんです。でも一体どう取り上げればいいのかとか、どう作ればいいのかとか、すごく難しくて。これはいつ解けるかわからないんですけど、でも難問と対峙しつつ手のひらの中に知恵の輪を持っているみたいな感覚でずっといるのが、私は好きなのかもしれないなと思っています。この知恵の輪は先輩たちも解こうとしてきたと思いますし、未来の人は私ほど苦労せずに分解できちゃうかもしれないんですけど、やっぱり現代の私は現代の大きな物語を描きたいと、どっかでそう思ってるんです。演出ももちろん大好きなのですが、私の場合、ゼロから生み出したいんだと思います。多分これはずっと死ぬまでそうなんじゃないかな。自分の性格なんだろうなという気がします。
藤田 非常に面白いです。なぜなら結局、書いた作品より演出の方が多いわけですよね。
五戸 そうですね。
藤田 何か必然だと思います。書きたいという思いがあって、劇作に対するリスペクトがあるからこそ、丁寧な演出ができるんだなっていう風に思いました。
五戸 ありがとうございます。
藤田 やはり、遠いようで近い、と五戸さんを思いました。
五戸 私もとても近さを思いました。めちゃめちゃおもしろかったです。

聞き手: 桒原秀一・平松香帆(広報部)
EMMA(担当理事)